うつ病の発症の原因とその症状をさぐる
2025年1月20日

うつ病は、何故発症してしまうのか
うつ病は、現代社会で多くの人が抱える深刻な問題です。厚生労働省のデータによると、日本では100万人以上がうつ病と診断されており、実際には診断を受けていない人を含めるとさらに多くの人がこの病に苦しんでいると考えられます。では、なぜうつ病は発症してしまうのでしょうか?
本記事では、うつ病の原因について 「生物学的要因」「心理的要因」「社会的要因」 の3つの観点から分かりやすく解説していきます。
1. 生物学的要因(脳やホルモンの働き)
① 脳内の神経伝達物質の異常
うつ病の発症には、脳内の「神経伝達物質」と呼ばれる化学物質の働きが大きく関係しています。特に、以下の3つの神経伝達物質が重要とされています。
- セロトニン(心の安定に関与)
- ノルアドレナリン(ストレスへの対処に関与)
- ドーパミン(やる気や快楽に関与)
これらの物質が不足すると、「気分が落ち込む」「何をしても楽しくない」「ストレスに弱くなる」といった症状が現れやすくなります。特にセロトニンの不足は、うつ病の大きな要因のひとつと考えられています。
② 遺伝的要因
うつ病は 遺伝的な影響を受けやすい病気 でもあります。たとえば、親や兄弟にうつ病を経験した人がいる場合、発症リスクがやや高くなることが研究で示されています。ただし、遺伝だけで決まるわけではなく、「ストレス」や「環境」との組み合わせによって発症することが多いと考えられています。

2. 心理的要因(性格や考え方の影響)
① まじめで責任感が強い性格
うつ病になりやすい人の特徴として、以下のような性格傾向が挙げられます。
- 完璧主義(100%の結果を求め、失敗を許せない)
- 責任感が強い(自分のミスを過度に責める)
- 他人に頼れない(助けを求めるのが苦手)
こうした性格の人は、ストレスを抱え込んでしまいやすく、心の負担が大きくなりやすいのです。
② 否定的な考え方(認知の歪み)
うつ病の発症には 「ものの見方」 も関係しています。たとえば、以下のような思考パターンを持っていると、うつ病になりやすいとされています。
- 「どうせ自分はダメだ」(自己否定)
- 「すべてがうまくいかない」(極端な悲観思考)
- 「人に迷惑をかけてはいけない」(過度な自己犠牲)
こうした考え方が強いと、ストレスに対する耐性が低くなり、精神的なダメージを受けやすくなります。

3. 社会的要因(環境やライフスタイルの影響)
① 過度なストレス
現代社会では、さまざまなストレスが人々の心に影響を与えています。特に、以下のようなストレスは、うつ病の発症リスクを高めます。
- 仕事のプレッシャー(長時間労働、パワハラ、人間関係の悩み)
- 家庭の問題(夫婦関係の悪化、育児ストレス、介護の負担)
- 社会的孤立(友人がいない、一人暮らしによる孤独感)
強いストレスが続くと、脳の神経伝達物質のバランスが崩れ、気分の落ち込みが慢性化しやすくなります。
② 生活習慣の乱れ(睡眠・食事・運動不足)
ライフスタイルも、うつ病の発症に影響を与えます。
✔ 睡眠不足 → 脳の回復ができず、気分が沈みやすくなる
✔ 栄養不足(特にビタミンB群・鉄分不足) → 神経伝達物質が正常に作られなくなる
✔ 運動不足 → ストレス発散ができず、気分の落ち込みが増える
特に 「睡眠不足」 は、うつ病の大きな原因のひとつです。
4. うつ病を防ぐためにできること
うつ病の発症を防ぐためには、日常生活の中でできる対策を意識することが重要です。
① ストレスをためすぎない
- 頑張りすぎない(適度に休むことを意識する)
- 人に頼る(一人で抱え込まず、信頼できる人と話す)
- 趣味やリラックスできる時間を作る(心の余裕を持つ)
② 生活習慣を整える
- しっかり睡眠をとる(最低6~7時間は寝る)
- バランスの良い食事をとる(ビタミンB群・鉄分を意識する)
- 適度な運動をする(ウォーキングやストレッチでもOK)
③ 否定的な思考を見直す
- 「完璧でなくてもいい」と考える
- 「自分を責めすぎない」習慣をつける
- 「小さな幸せ」に目を向ける(感謝の気持ちを持つ)
これらの習慣を意識することで、うつ病のリスクを下げることができます。

うつ病の具体的な症状とは
うつ病は、単なる「気分の落ち込み」ではなく、心と体の両方に深刻な影響を与える病気 です。その症状は人によって異なりますが、大きく分けると 「精神的な症状」「身体的な症状」「行動の変化」 の3つの側面で現れます。
本記事では、うつ病の具体的な症状について、できるだけ分かりやすく詳しく解説していきます。
1. 精神的な症状(心の変化)
うつ病の主な特徴は 「強い気分の落ち込み」 ですが、それ以外にもさまざまな精神的な症状が現れます。
① 強い抑うつ気分(気分の落ち込み)
- 朝から気分が沈んでいる(特に朝がつらい「日内変動」)
- 楽しいことがあっても気持ちが晴れない
- 理由もなく悲しくなり、涙が出ることがある
うつ病になると、ポジティブな出来事があっても喜びを感じにくくなり、何をしても気分が晴れない状態が続きます。
② 興味や喜びの喪失
- 趣味や好きなことに興味がなくなる
- 何をしても楽しいと感じられない
- 以前は好きだったことも面倒に思えてしまう
たとえば、音楽が好きだった人が「音楽を聴く気になれない」「好きだった映画が楽しめない」と感じることがあります。
③ 強い不安や焦り
- 何か悪いことが起こるのではないかと常に不安を感じる
- 根拠のない焦燥感(そわそわする感覚)がある
- 落ち着かず、じっとしていられない
このような不安感は、特に夜や朝方に強くなることが多く、心が休まらない状態が続きます。
④ 自己否定や罪悪感が強くなる
- 「自分は価値のない人間だ」と感じる
- 「周囲に迷惑をかけている」と思い込む
- 過去の失敗を思い出して、強く後悔する
うつ病になると、必要以上に自分を責めてしまい、「生きている意味がない」と感じることもあります。

2. 身体的な症状(体の変化)
うつ病は心の病気ですが、実は 身体にもさまざまな不調 が現れます。
① 睡眠障害(不眠・過眠)
- 夜に眠れない(入眠困難)
- 夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)
- 早朝に目が覚めてしまう(早朝覚醒)
- 逆に、昼間もずっと眠い(過眠)
特に「朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)」は、うつ病の特徴的な症状のひとつです。
② 食欲の変化(減少・増加)
- 食べる気がしない、味を感じない(食欲減退)
- 無理に食べても美味しく感じられない
- 逆に、食べすぎてしまう(過食)
多くの人は「食欲がなくなる」傾向がありますが、中には「食べることで気を紛らわせようとして過食になる」人もいます。
③ 頭痛や体の痛み
- 頭が重く感じる、締めつけられるような痛み
- 肩こりや腰痛がひどくなる
- 体がだるく、常に疲れている感じがする
これは、ストレスによる自律神経の乱れが影響していると考えられています。
④ 胃腸の不調
- 食べるとすぐにお腹が痛くなる
- 下痢や便秘を繰り返す
- 胃がムカムカする、吐き気がする
特に「胃の不快感」や「便秘・下痢の繰り返し」は、うつ病の人によく見られる症状です。
3. 行動の変化(生活への影響)
うつ病の症状は、日常生活や人間関係にも大きな影響を及ぼします。
① 何をするのもおっくうになる
- 仕事や家事ができなくなる
- 歯を磨く、着替えるといった基本的なことすら面倒になる
- 外出する気力がなくなり、家に引きこもるようになる
これは、「意志が弱い」わけではなく、脳の機能が低下して「やる気を出せなくなっている」状態です。
② 周囲とのコミュニケーションが減る
- 人と話すのが面倒になる
- LINEやメールの返信ができなくなる
- 職場や学校を休みがちになる
うつ病になると、人と関わること自体が負担になり、連絡を取るのが難しくなることがあります。
③ 自傷行為や希死念慮(死にたい気持ち)
- 「消えてしまいたい」と思うことが増える
- 実際に自傷行為をしてしまう
- 「生きる意味がない」と感じることが多くなる
こうした症状が現れた場合は、すぐに専門家(医師・カウンセラー)に相談することが大切です。

4. うつ病の症状が現れたらどうすればいい?
もし、上記のような症状が続いている場合、以下のことを試してみてください。
① 無理に頑張ろうとしない
- 「気合でなんとかしよう」と思わない
- できることだけを少しずつやる
- 休むことは「甘え」ではなく「回復のために必要」なこと
② 生活リズムを整える
- 朝起きたら太陽の光を浴びる
- 少しでも体を動かす(散歩など)
- 栄養バランスの良い食事をとる
③ 相談する(専門家・家族・信頼できる人)
- 病院の受診を検討する(うつ病は「治療できる病気」)
- カウンセリングを受ける(話すだけでも気持ちが軽くなることがある)
- 信頼できる家族や友人に話す(「助けて」と言うのは勇気のいることですが、とても大切です)
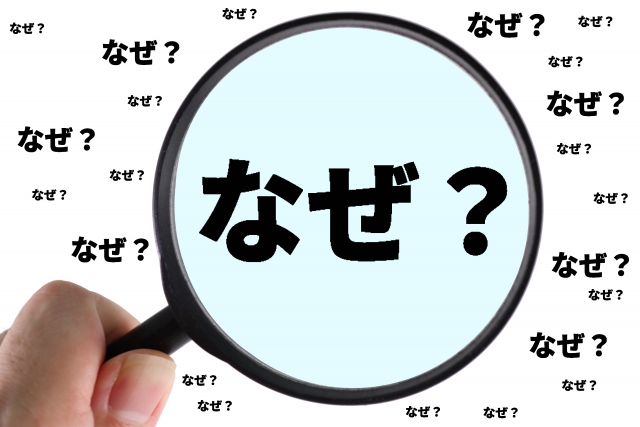
うつ病の発症の原因とその症状をさぐる
うつ病の発症の原因とその症状とは!
現代はストレス社会です。現代社会は、時の流れとともに大きな変化を繰り返しています。その変化の繰り返しが時としてストレスとなって行く事がありますので、現代社会はストレス社会とも言われています。
そのストレスが適度であれば、頑張ろうとは励みになります。しかし、その範囲を超えてしまうと心のバランスが崩れていきます。その結果、うつ病等を発症する事があります。うつ病を発症する事により、本来の自分が失われて様な感覚になり、お仕事や家事・育児などが出来なくなっていきます。
うつ病は、精神的なストレスだけでなく、脳や体内のホルモンバランスの乱れ と深く関係しています。特に、ストレスホルモン(コルチゾール) がうつ病の発症や症状の悪化に関与していることが明らかになっています。
本記事では、うつ病とストレスホルモンの関係について、できるだけ分かりやすく解説していきます。
1. ストレスホルモンとは?
ストレスホルモンとは、ストレスを受けたときに体内で分泌されるホルモン のことです。その中でも特に重要なのが 「コルチゾール」 というホルモンです。
コルチゾールの主な働き
コルチゾールは、副腎皮質(腎臓の上にある副腎という臓器)から分泌され、以下のような役割を担っています。
- ストレスへの適応(ストレスがかかったときに体を守る)
- 血糖値の調整(エネルギーを確保し、脳や体が正常に働くようにする)
- 炎症を抑える(免疫反応を調整し、過剰な炎症を防ぐ)
- 血圧の維持(循環器系のバランスを整える)
通常、コルチゾールは朝に分泌量が多くなり、夜になると減少する ことで、体内リズムを整えています。
しかし、慢性的なストレスを受けると、コルチゾールが過剰に分泌され、体や脳に悪影響を及ぼす ことが分かっています。
2. ストレスホルモンとうつ病の関係
ストレスが長期間続くと、コルチゾールが異常に増えたり、逆に適切に分泌されなくなったりします。この変化が、うつ病の発症や悪化につながる と考えられています。
① 慢性的なストレスでコルチゾールが過剰に分泌される
長期間にわたるストレス(仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、トラウマなど)が続くと、脳の視床下部-下垂体-副腎系(HPA軸)が活性化し続け、コルチゾールが過剰に分泌されます。
その結果、以下のような問題が発生します。
- 脳の機能が低下する(特に記憶を司る「海馬」がダメージを受ける)
- 感情を調整する「前頭前野」の働きが低下する(気分のコントロールができなくなる)
- セロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質のバランスが崩れる(喜びや楽しさを感じにくくなる)
これらの変化が、うつ病の発症や症状の悪化につながるのです。
② コルチゾールの過剰分泌による具体的な影響
(1) 海馬の萎縮(記憶力や集中力の低下)
海馬は、記憶や学習を司る重要な脳の領域です。しかし、コルチゾールが長期間にわたって過剰に分泌されると、海馬が萎縮する ことが研究で明らかになっています。
その結果、以下のような症状が現れます。
✔ 物事を思い出しにくくなる
✔ 集中力が続かない
✔ 新しいことを覚えにくくなる
海馬の機能が低下すると、「何をするにもやる気が出ない」「考えがまとまらない」といった状態になりやすくなります。

(2) 前頭前野の機能低下(感情コントロールの乱れ)
前頭前野は、感情のコントロールや思考を司る部分です。コルチゾールの過剰分泌によって前頭前野の働きが低下すると、感情の調整が難しくなる のです。
その結果、
✔ ちょっとしたことでイライラしやすくなる
✔ 悲しみや不安が強くなりやすい
✔ ネガティブな思考が止まらなくなる
前頭前野の機能が低下すると、「自分はダメだ」「何をしても意味がない」といった自己否定の思考が強くなる ため、うつ病の症状が悪化しやすくなります。
③ コルチゾールの分泌が低下するとどうなる?
一方で、ストレスが長期間続いた後、コルチゾールの分泌が極端に低下してしまう こともあります。これは、副腎が疲れ切ってしまい、ホルモンを正常に分泌できなくなる状態(副腎疲労)です。
コルチゾールが不足すると、以下のような症状が現れます。
✔ 慢性的な疲労感(何をしても疲れる)
✔ 低血圧やめまい
✔ 朝起きられない、倦怠感が続く
✔ やる気がまったく出ない
このような状態に陥ると、うつ病の症状がさらに悪化し、日常生活が困難になる 可能性があります。

3. うつ病の予防とストレスホルモンのコントロール方法
うつ病を予防し、ストレスホルモンの影響を最小限に抑えるためには、生活習慣を整えることが非常に重要 です。
① 規則正しい生活を心がける
- 毎朝同じ時間に起きて、朝日を浴びる(体内時計を整える)
- 適度な運動をする(ウォーキングやヨガなど)
- 夜更かしを避け、十分な睡眠をとる
② マインドフルネス瞑想を取り入れる
マインドフルネスは、ストレスホルモンを抑え、心を安定させる効果 があることが科学的に証明されています。
✔ 深呼吸を意識する
✔ 今この瞬間に集中する
✔ ストレスに振り回されない心を育てる
③ バランスの取れた食事を意識する
- オメガ3脂肪酸を多く含む食品(青魚、ナッツ類)を摂る
- ビタミンB群(豚肉、卵、大豆製品)をしっかり摂る
- 砂糖や加工食品を控え、腸内環境を整える

うつ病への対応と支援
うつ病の症状が現れるプロセス
うつ病は徐々に進行することが多く、以下のようなプロセスをたどることがあります。
- 初期段階:
ストレスや疲労感が強く、軽い気分の落ち込みや意欲の低下が見られる。 - 進行段階:
心理的、身体的症状が悪化し、日常生活に支障をきたす。 - 重度段階:
自殺念慮や無力感が強まり、緊急の専門的なサポートが必要になる。
うつ病への対応と支援
(1) 早期発見と治療
- 症状を感じたら早めに専門家に相談することが重要です。精神科や心療内科での診断が適切な治療への第一歩となります。
(2) 治療方法
- 薬物療法: 抗うつ薬で神経伝達物質のバランスを整える。
- 心理療法: 認知行動療法(CBT)やマインドフルネス療法が効果的です。
- 生活リズムの改善: 規則正しい生活を心がける。
(3) 周囲のサポート
- 家族や友人の理解と支援が回復に大きな役割を果たします。
- 職場や学校での柔軟な対応も重要です。
まとめ
うつ病は、多くの要因が関与する複雑な疾患ですが、適切な理解と治療を通じて回復が可能です。その発症原因を探り、症状を早期に把握することで、効果的な対策を講じることができます。焦らず、自分のペースで専門家の支援を受けながら改善に取り組むことが大切です。

私たちの目的は症状の完治
私たちは、うつ病の辛い症状を、緩和させたり改善する事を目的にしているのではありません。
私たちの目的は、うつ病の辛い症状の完治を目指しています。
私たちの言う完治とは、
1、お薬などを飲まずに通常の生活が送れる事。
2、この病気の怖いのは再発です。(その再発が起きない自分を作る事。
ですから、うつ病の症状をお持ちの方は、是非、一度ご相談ください。
そして、本来の自分を取り戻して、あなた自身の役目・役割を果たす事によって、より豊かな社会づくりに貢献できる自分になってください。
その事が、私たちの願いでもあるのです。
【リンクのご案内】
〇カウンセラー・佐藤さんに聞く「マインドフルネス」実践と“想い”

