うつ病になるとどうなるのか
2023年9月24日

うつ病になると、どうなるのか、
仕事ができなくなるとか、人との会話をできなくなるとか、様々な症状が起こって来ます。
また、そのような状態がなかなか改善しないとか、くり返し起こる事により、死にたくなるというような症状が起きて来ます。
うつ病になると、どうなるのか
心の変化
強い抑うつ感
→ 理由もなく悲しい、虚しい、何も楽しくない。興味・喜びの消失
→ 今まで好きだったことにも興味がわかず、無関心になる。自己否定・罪悪感
→ 「自分はダメな人間だ」「迷惑しかかけていない」と思い込む。決断力・集中力の低下
→ 些細なことも決められず、考えがまとまらなくなる。
身体の変化
不眠・過眠
→ 夜中に目が覚める、寝つけない。逆に過度に眠り続けることも。食欲不振・過食
→ 食べられなくなるか、逆に食べすぎてしまう。倦怠感・疲労感
→ どれだけ休んでも疲れがとれず、動くのがつらくなる。頭痛・胃痛・肩こりなどの身体症状
→ 検査しても異常がないのに不調が続くことが多い。
行動の変化
人と会うのがつらくなる
→ LINEや電話も億劫、孤立しがちになる。仕事や学業への意欲喪失
→ 行けない、手につかない、ミスが増える。最悪の場合、自死念慮
→ 「消えてしまいたい」「もう楽になりたい」という思いが生まれる。
さらに深いところでは
うつ病になると、物事の受け取り方そのものが変わってしまいます。
✔️ 他人の言葉を否定的にしか受け取れない
✔️ 過去の失敗ばかり思い出して自分を責める
✔️ 未来に希望を感じられなくなる
この状態が続くと、生きる力がどんどん削がれていきます。

ではなぜ、うつ病になるのでしょうか。
うつ病が起きる仕組み
ストレスを受ける出来事(有意識・無意識)があって、対処できないとか、見通しが立たない、耐えられないと思うと、次のような、つらい考えを繰り返すことが多くなって来ます。
解決策が見えず、不快な状況が持続してしまいます。
A)繰り返されると「うつ病」になりやすい考え=不満、嫌悪、怒り、憎しみ、後悔、悲哀、絶望などの感情を起こす思考
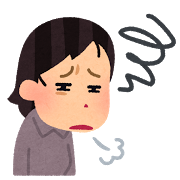
このような考え、感情はけして悪いわけではなくて正当なことが多く、短時間で、回数が多くなければ、うつ病になることはありません。また、このような考えを起こすと以下のような身体反応が起こります。
★(1)交換神経が興奮する。
★(2)副腎皮質から
ストレスホルモンが分泌される。
交感神経の興奮やストレスホルモン(コルチゾール、ゲルココルチコイド)が分泌されると、身体の反応(胸がくるしく感じたり、心臓がドキドキしたり、呼吸が荒くなったり)があったり、気分が悪くなったりします。
それを感じて、つらい考えを繰り返す事があります。
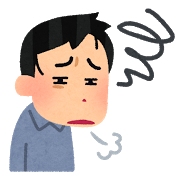
感情が起きたり、交感神経が興奮したり、ストレスホルモンが分泌されても、考えることをやめたり、具体的な解決策がみつかると、この循環がとまる。

しかし、解決策がないままに、不満、嫌悪などの思考を繰り返えすと、うつ病になるリスクが高まります。
精神症状のしくみ
(1)自律神経の持続的興奮
↓
自律神経失調
↓
内臓などに症状
↓
精神症状
(2)ストレスホルモン
↓
前頭前野や大脳辺縁系などが傷つく
↓
精神症状
不安障害やパニック障害のしくみ
(パニック障害、対人恐怖、全般性不安障害、外傷後ストレス障害など)の場合は、急に起きる不安、恐怖の感情や身体反応(心臓のドキドキ、胸の痛み、息苦しさなど)、発作(パニック発作)を嫌って、行動が制限(回避、逃避)されます。
ストレスホルモンの過分泌の影響
ストレスを受ける出来事があると、嫌悪、不満、後悔、悲哀、絶望、怒りなどの感情を起こすような思考を繰り返す。
そうすると交感神経や副腎皮質が興奮する。
交感神経が興奮することが繰り返されると、種々の身体症状があらわれます。
また、うつ病患者の前頭前野や海馬(記憶の形成)の容積が小さいと言われています。
副腎皮質が元進して、ストレスホルモンが分泌され続けると、前頭前野や海馬の細胞を傷つけてしまうようです。
前頭前野や海馬のネットワークを形成する樹状突起スパインが減少するとか、グリア細胞が減少すると言われています。
うつ病患者の前頭前野や海馬(記憶の形成)の容積が小さくなるのは、そのためかもしれません。
そうすると、前頭前野や海馬の機能低下の症状があらわれるようです。
心理的ストレス
↓
感情が起きる
↓
ストレスホルモンが分泌
↓
前頭前野、海馬の機能がそこなわれる
↓
精神機能の低下(集中できない、意欲ない、など)

さらに、このような精神症状や身体症状を感じて、つらい思考をくり返していると治りにくい状態になって行きます。
前頭前野の働きとは
○感情脳を抑制したり、調整したりする。
○衝動の抑制、規範に則った行動、適切な行動の選択。
○思考、創造、他人とのコミュニケーション、意思決定。
○感情の制御、行動の抑制。
○記憶のコントロール、意識注意の集中、注意の分散。
○意欲、自発性、喜び。
○ワーキングメモリ。 (作業記憶)
うつ病になると、こうした機能が低下してしまいます。

ではどうしたらいいのか
・安心できる場所で、今の自分をそのまま受け入れてもらうこと
・マインドフルネスの実践で「今ここ」を穏やかに感じること
・孤独の中にそっと寄り添う存在がいること
それだけでも、人の心は少しずつ回復する力を取り戻します。
薬だけでは届かない領域を、静かに見つめ、丁寧に解きほぐしていくことが大切なんです。
【リンクのご案内】
〇カウンセラー・佐藤さんに聞く「マインドフルネス」実践と“想い”

