- ホーム
- マインドフルネスとは、
マインドフルネスとは、

「マインドフルネスとは何か」――その問いに、私自身の経験と実践を通じて向き合ってきました。
このページでは、「マインドフルネス」という言葉が単なる流行語ではなく、心の奥深くに向き合い、自分らしく生きていくための“生き方”であることを、私自身の視点から丁寧にお伝えしています。
マインドフルネスは、「今、この瞬間」に意識を向けて、思考や感情、体の感覚を評価や判断なしに、そのまま受け止める心の姿勢です。現代社会はスピードが速く、情報に溢れ、不安やストレスが日常的に私たちを揺さぶります。その中で、「立ち止まり、自分の内側の声に耳を傾けること」は、多くの方にとって難しいことかもしれません。
私自身、多くの方とマインドフルネスの実践をともにしてきました。うつ病や不安症、ストレスによる心身の不調、人間関係の苦しみ…。それぞれが抱える悩みは異なりますが、共通して言えるのは、「自分を責めすぎている」「過去や未来の思いにとらわれている」状態から抜け出せずにいる、ということです。
このページでは、マインドフルネスの本質と効果、そしてなぜそれが現代の私たちに必要なのかを、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明しています。西洋的な瞑想技法として知られるマインドフルネスですが、実はその根底には、私たち日本人が大切にしてきた「今を生きる」「無常を受け入れる」といった文化や哲学が息づいています。私はその視点から、仏教や東洋思想、そして西田哲学とも接続しながら、独自のマインドフルネス心理療法を展開しています。
このページを訪れた方の多くは、「何かを変えたい」「でもどうしたらいいかわからない」と感じているのではないでしょうか。そうした方々に、マインドフルネスはそっと寄り添います。急がず、無理をせず、「今ここ」に戻ること。それが、自分らしさを取り戻し、心の苦しみから少しずつ自由になっていく道の第一歩です。
私たちのマインドフルネスは、ただの技法ではありません。生き方を見つめ直し、自分と向き合う時間を大切にするプロセスです。このページを通じて、マインドフルネスの真の意味を感じていただければ嬉しく思います。そして、もし共感していただけたなら、ぜひ一歩踏み出してみてください。あなたの人生が、少しずつ穏やかに、軽やかに変わっていくことを願っています。
マインドフルネスとは、
マインドフルネスとは、今この瞬間の自分の心や体の状態に意識を向け、ありのままを受け入れる心の持ち方です。
私たちは普段、過去の出来事を思い返したり、未来の不安を考えたりして、心が今ここにない状態になりがちです。マインドフルネスは、呼吸や体の感覚、周囲の音など「今」に意識を向けることで、余計な考えから距離をとり、心の安定を取り戻す方法です。仏教の瞑想法を基に、現代ではストレス軽減やうつ、不安の改善、集中力向上のための心理療法としても活用されています。難しいことはなく、1日数分の呼吸に意識を向けるだけでも効果が期待できます。忙しい現代人にこそ役立つ、心のセルフケア法です。
そのマインドフルネスのルーツは、
マインドフルネスのルーツは日本の座禅にあると言われています。
その座禅には、只管打坐を唱えた福井県永平寺の道元禅師(曹洞宗)と、日本禅宗の祖と言われ公案を唱えた栄西(臨済宗)との二派があります。マインドフルネスは公案を用いる事はありませんので、宗教的な事を排除して参加者の心を整えていく事にスポットを当てた手法になります。
私たちの住む現代社会はストレス社会と言われています。その現代社会ではストレスから逃れる事はできませんので、複雑に変化を繰り返して行く社会構造の中で、多くの人が常にイライラしている状態になっていると思われます。
そのような中にあってもマインドフルネスを取り入れる事により、ストレスから逃れる事を考えるのではなく、ストレスの中にいても自分らしさを失わずに、自分らしく生きていく事が出来ます。また、その延長上にうつ病や不安症(不安障害・パニック障害)、強迫神経症等で悩む方々をサポートする事が可能になるのです。
パワーアップマインドフルネス
私がご提供するパワーアップマインドフルネス心理療法は、単なる技法の提供ではありません。人生を通して深めてきた人間理解と、苦しみに寄り添う姿勢をもとに構築された、心に深く届く実践法です。
そして、自分の中に眠っている内なるパワーを引き出して行きます。
私自身、20代から社会貢献を志し、ボランティア活動に力を注いできました。その中で、うつ病に苦しむ知人がマインドフルネスの実践によって次第に回復していく姿に衝撃を受けたことが、今の活動の原点です。この出来事を契機に、私の人生の中心は「苦しむ人の心に寄り添うこと」へと移っていきました。
現在では、マインドフルネス瞑想療法士として、うつ病・不安障害・パニック障害・PTSDなど、現代社会に多い心の課題を抱える方々に対して、実践的なサポートを行っています。活動歴は15年を超え、延べ650名以上の方と出会い、無料相談を通してその心の声に耳を傾けてきました。病院に通っても改善が見られない方、薬の副作用に不安を感じている方にとって、心の回復に向けた“もう一つの道”として、この療法は支持されています。
マインドフルネスの真髄に触れる
今回はそのマインドフルネスの原点である、中国の禅宗の初祖である達磨大師に付いて、また道元禅師の唱えた只管打坐に付いて眺めて行きながら、マインドフルネスの真髄に触れてみたいと思います。その中で本編をお読みいただく方がより深く・より広くマインドフルネスの真髄を掴んでいただき、より多くのうつ病や不安症(不安障害・パニック障害)、強迫神経症等で悩める方々のサポート活動の糧になる事を願っています。

達磨大師像
中国の禅宗の初祖 達磨大師とは
中国における禅宗の初祖・達磨大師は今から1600年ほど前、南インドにあるカンチープラム(香至国)の第三王子として誕生し、幼名は菩提多羅(ぼだい たら)といいました。
若い頃に父である国王が亡くなり、菩提多羅王子は国政を二人の兄に頼み、お釈迦様から二十七代目にあたる般若多羅尊者のもとに出家し、『菩提達磨』の僧名を頂きました。
師について修行すること四十年に及び、般若多羅尊者から釈尊正伝の第二十八代目を継承しましたが、師より「六十七年間はインドを布教し、その後に中国に正法を伝えなさい」と遺言され、それに従って老年になってから、海路を三年かかり中国・広州の港に上陸しました。
そして梁の武帝と問答し、縁かなわず揚子江を渡って洛陽の都のはずれ、嵩山少林寺の裏山の洞窟に住み、面壁九年の坐禅をするうちに求道者・神光が現れ、その熱意に感じ中国で始めて弟子をとり、慧可と名付けました。
この慧可にすべてを伝え、中国に禅宗の基礎を築かれたのですが、その教えを理解できない者たちによって毒殺され、熊耳山定林寺に葬られました。
出典:高崎市少林山達磨寺のホームページより

高崎市少林山達磨寺
達磨大師禅の思想
中国の禅宗の初祖・達磨大師が、禅の神髄を端的に言い表した内容が「達磨大師の四聖句」と言われています。現在でも、その事を大切に受け継いで今に至っています。その達磨大師の四聖句とは以下になります。
「不立文字」 「教外別伝」 「直指人心」 「見性成仏」
この四聖句から、達磨大師の神髄に触れながら、マインドフルネスの神髄に触れていきたいと思います。
四聖句の伝えることは、経典や言葉にたよることなく(不立文字)、説かれた言葉以外に真理が存在し(教外別伝)、仏性をもつ本来の自分に気がつくこと、それが悟りである(直指人心、見性成仏)ということになるようです。そこで大切な事は、この四聖句はそれぞれ別々に独立したものではなくて、それぞれ密接なつながりを持っていることです。
以下に順を追って説明していきます。

「不立文字」
悟りの境地は文字では言い表すことの出来ない直接的な経験(純粋経験)になります。
それは、その経験をしたもの(観じとったもの)しかわからない経験になります。ゆえに、
その内容や感覚はその人にしかわからないので、伝える事や言い表すことが困難な事になります。このことから、禅は心をもって心を伝えると言う事から、弟子が師匠に口頭でその内容伝え、代々伝承していくこと重視しています。
マインドフルネスを繰り返すことによって得られる境地(気づく・観じる)も、
実践する各々が得られる事であって文字で表すことが出来ない純粋経験であると捉えています。その事を、参加者からまた指導者からセッションを通じて、参加のそのたびに参加者により沿った内容を口頭で伝え、受け継いでいくこと重視しています。

「教外別伝」
「教外別伝」禅の真髄は、経典の内容を越えたところにある!
禅宗では、釈尊の示された以心伝心の教えを教外別伝と言っています。わかりやすくいいますと、釈尊の教えを教内の方といい、以心伝心(ことばでは表わせない悟りや真理を心から心へと伝えること)の教えを教外別伝と言っています。
他の仏教の宗派は経典を中心とした数学を行っているようですが、禅の場合は経典を中心とする事は多くはありません。それは、悟りを得る為に様々な経典や、先人の著作物やその語録などを読んでも、肝心要なところ(以心伝心の教え)では役にはたたない事があるようです。と言っても、それらのものを否定しているものでもありません。大切な事は、どんな経典であっても、その内容に囚われず束縛されないことが大切になると言っているのです。その事が、ありのままの自分の眼をもつことにつながって行く事になります。
道元禅師はここの事を例えて、
「百人の僧侶がいれば百の経典が出来る」と言っているようです。その為に、文字に書かれたもの、経典や祖師の残した書物や語録にも、一切とらわれないようにすることが、とても大切になります。
たとえば、あなたが車の運転を習うとした場合、いくら教則本を繰り返し読んでも、絶対に上手に運転ができるようにはなりません。それは、その教則本が悪いのではありません。そこで他の物に変えたところで、運転が上手になることはありません。上手に車の運転が出来るようになるのには、自動車教習所などで直接指導員に指導を受けながら、繰り返し練習、実践しなければ、どうにもならないのである。

早い話、マインドフルネスもそれと同じです。
市販されている書籍や参考テキストなど、最近ではインターネット等もありますが、それらを読めば・又見れば、その雰囲気は何となく、つかめたような感じになるかもしれません。そして時として安易に指導者になったような気分を感じることがあると思います。
しかし、マインドフルネを体得した指導者の基で繰り返し・繰り返し実践し続けて行かなくては、奥深いマインドフルネスの真髄を掴む事は出来ません。
「教外別伝にある」、それは市販されている書籍や参考テキストなどの内容を絶したところにあるといって過言ではありません。

「直指人心」
「直指人心」あれこれ考えずに、じかに自分の心をみつめよ!
いたずらに、眼を外に向けてもあれこれと模索しても時間の無駄で埒(らち)があかない。あれこれ考えずに自分自身の心を見つめよ、と言っているのです。
ところで、じかに自分自身の心をみつめよ、といったところで心とはどうゆうものなのでしょうか。

不生禅を唱えた禅僧、盤珪(ばんけい)は
「人間の心とは、本来、鏡のようなものである」と言っています。盤珪によれば、人間の心は、きれいな物を映すと、それが映されるとの事です。汚い物を映すと、そのまま汚いものが映し出される。そのような鏡が人間本来の心の正体であると言っています。鏡であればこそ、きれいなものであれ、汚いものであれ、当然、なんでも映しだしますが、鏡の本来の価値には全く何の変化もありません。その事を忘れ、執着するからこそ、心の鏡が曇ってしまうだと説いています。その曇りから迷いが生じて、いろいろと悩むことになるわけであると言っています。その為にまずは、自分の心を見つめ直す必要があるのだと説いています。
マインドフルネスは、
自身のこころに・自身の脳裏に浮かび上がってくる、日々の様々なストレスや不安や嫌な思考、また身体的な変調などを、あれこれと考えず・膨らませずに静かに眺めて静観せよ、ということなのです。そして、静かにゆっくりと息を吐いていく事を繰り返すことを説いています。このことを、繰り返して行って先に結果として「自分のこころを見つめる」事となります。
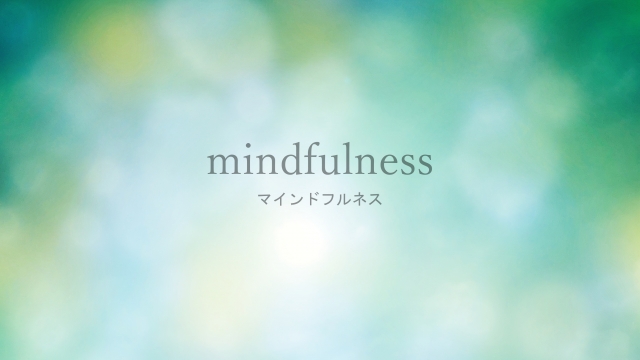
「見性成仏」
「見性成仏」仏性に目覚めればおのずと仏になる!
達磨大師の四聖句の最後の句であり、最も重要なのが見性成仏になります。
この見性成仏の句が現れた最古の文献は、臨済の師であった黄檗(おうばく)の『伝心法要』にあると言われています。「ここに至ってまさに知る。祖師(達磨)が西よりきたり、直指人心、見性成仏は言説にあらざることを」とあります。
見性成仏とは、自分が備えている仏性に目覚めれば、仏に成るという意味です。仏になるとは、結局、本来の自分に戻ることにつきます。本来の自分に戻ることが、禅の本質です。
坐禅を通して、直指人心、見性成仏する。
一人一人がそれぞれ本来の自分に返るのです。そこで初めて本当の意味での個性(自分らしさ)が発揮されるのです。だからこそ、悟りに至る体験は人それぞれで違うのです。そう言う意味でも、禅は実際に体験しなければ話にならない。その為にも、正しい師匠に付く事が不可欠になります。
禅は理屈ではない。頭で考えたり、覚え込もうとするものではない。禅の悟りというものは、自分の身体の中にすでに備わっている。それに、どう気付きくのか、自分の備わっている本来の自分を確認する作業が禅になります。
マインドフルネスは宗教ではありません。
そこで坐禅に出てくる「見性成仏とは」とか、「仏性に目覚めれば」とか、「仏に成る」とか、という事を説いたり・言うことは一切ありません。

マインドフルネスの目標は自分らしく生きていく事
「自分らしく生きていく事」を目標に掲げています。只、「自分らしく生きていく」とは、自分のおもいどうりになったり、自分の好き勝手に生きる事とは違います。自分らしくとは、一見簡単に出来るように思えますが、現代のストレス社会の真っ只中ではとても難しい環境化にあります。
例えば、お仕事や家事育児等の様々な活動を、一生懸命に行っていても「自分は何のために生きているのかが、わからない」とか「生きがいや、張り合いを感じない」方が多い現実があります。そんな現実は、砂をかむような日々だと思います。少なくとも、そんな日々は自分らしく生きて行く事とはかけ離れているのではないでしょうか。
その時々に、自分の置かれた環境や境遇を、嫌悪したり・悲観することなく、自分の置かれた環境や立場・境遇を理解しながら、自分の役目・役割を果たしていくことが出来れば、「自分なりの生きがいや、張り合いを感じる」事が出来ます。そのことが結果として「自分らしく生きて行く事が可能になります。
奇妙に思われるかもしれないが、
禅の悟りは特別な体験であり、しかも特別な体験ではない。
あくまでも、本来の自分に戻り、本来の面目そのものになりきる事だからです。結局、当たり前のことに過ぎないのだが、その当たり前の事が非常に難しく、かつ限りなくありがたい事なのです。
達磨大師は、無功徳を示された。確かに無功徳であるが、それは同時に、なにものにもかえがたい功徳そのものです。
初心者がマインドフルネスに取り組み始めると、
次第にざわざわしていたこころが落ち着き始めてきます。すると、自身の気が付かなった事に次第に気づいて来るという事が起きてきます。その事に驚いたり・焦ったりすることがあります。「何故なんだ」とか「どうしたのか」と思う事です。
その事をこころ静かに眺めてみると、特別な事ではなく「当たり前の、ごく自然な事」であることに、気づかされる事が多々あります。そこで、さらに冷静にその事を眺めなおしてみると、今まで自身が気付かなかっただけの事だと言うことに、気づかされる体験を繰り返して行きます。
普段の生活の中では、当たり前のことに過ぎないのですが、その当たり前の事に気づかされる事が非常に難しく、かつ限りなくありがたい事なのです。
その繰り返しの中で、本来の自分に気づき、本来の自分に戻り、本来の姿そのものになることに、つながって行く事になります。そして、自分らしく生きて行く事が可能になります。
その事が、マインドフルネスで言う「自分らしく生きる」、「自分らしく生きていく」事になります。
達磨大師は「禅の無功徳を示された。」と言われていますが、
「本来の自分に戻る」、もともとの自分にもどる(帰る)のだから無功徳と言うことはマインドフルネスにも通じることです。
それは同時に、なにものにもかえがたい功徳そのものです。と達磨大師が言っているように感じています。
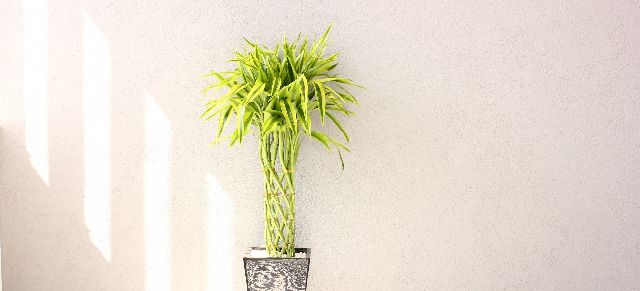
マインドフルネスは宗教ではない。
私たちは、マインドフルネスを知らない人たちの為に、マインドフルネスを理解していただく為に色々な手立てを用います。しかし、マインドフルネス自体に形や方式等がない為に、理解していただくことに苦心する事が多々あります。そんな時に、仏教用語や坐禅や只管打坐を引用させていただきます。
しかし、私たちが行うマインドフルネスは宗教ではありません。その事を具体的に言いますと、宗教とは以下に引用させていただきました要件があります。私たちが行っているマインドフルネスにはその要件がありません。(宗教的な活動は一切行っておりません。)
宗教とは、
一般に、人間の力や自然の力を超えた存在への信仰を主体とする思想体系、観念体系であり、また、その体系にもとづく教義、行事、儀礼、施設、組織などをそなえた社会集団のことである。なお広辞苑では「神または何らかの超越的絶対者あるいは神聖なものに関する信仰・行事」としている
・宗教団体の要件
○ 教義をひろめる
宗教には教義があります。それを人々にひろめる活動をしていなければなりません。
○ 儀式行事を行う
宗教活動の一環として日頃から儀式行事が行われていなければなりません。
○ 信者を教化育成する
教義の宣布によって信者を導くことが行われ、信者名簿等も備わっている。
○ 礼拝の施設を備える
邸内施設ではなく、公開性を有する礼拝の施設がなければなりません。
これらの要件は、宗教法人が存続するための条件でもあります。
出典:文化庁‐宗教法人運営のガイドブックより
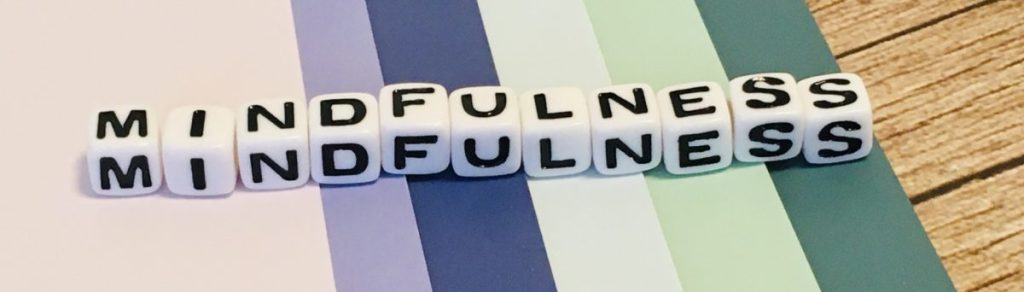
マインドフルネスのデメリットとは、
マインドフルネスは多くのメリットがありますが、状況や実践の仕方によってはいくつかのデメリットや注意点もあります。以下に主な点を挙げます。
1. 一部の人には逆効果になることがある
・トラウマやPTSDを持つ人がマインドフルネスを実践すると、過去の辛い記憶や感情が強く浮かび上がり、逆にストレスが増すことがあります。
・深く内面に向き合うことで、不安感や抑うつ感が悪化するケースもあります。
2. 即効性がない
・マインドフルネスは習慣化することで効果を発揮するため、短期間で劇的な変化を期待すると、「効果がない」と感じることがある。
・継続することで変化が現れるが、継続が難しいと感じる人もいる。
3. 非現実的な期待を抱きやすい
・「マインドフルネスをやればすべての悩みが解決する」と思うと、実際に効果を感じられないと落胆し、逆にストレスになることがある。
・うつ病や強い不安症の場合、マインドフルネス単独では十分な改善が難しく、他の治療法(薬物療法やカウンセリング)との併用が必要な場合もある。
4. 「思考を止める」ことと誤解されやすい
マインドフルネスは**「思考をなくす」ものではなく、「思考を客観視する」ものだが、間違った理解で取り組むと、「できない」と挫折する原因になる**。
5. 過度に実践すると逆効果になることも
研究によると、過度にマインドフルネスを行うと、感情の鈍化や現実逃避につながることがある。
現実の問題を解決せずに「ただ瞑想して気持ちを落ち着ける」ことに依存すると、問題が放置される可能性もある。
6. 文化的・宗教的な違和感を持つ人もいる
マインドフルネスは仏教の瞑想を起源としていますが、宗教色を感じて抵抗を持つ人もいる。
宗教的なものではなく、科学的・心理療法的な技法として取り入れることが重要。
まとめ
マインドフルネスは、多くのメンタルヘルスの問題に効果的ですが、適切に実践しないと逆効果になったり、過度な期待が裏目に出たりすることもあります。
✔ 効果を急がず、少しずつ習慣化すること
✔ 必要に応じて専門家のサポートを受けること
✔ 他の治療法と組み合わせてバランスよく活用すること
こうした点を意識することで、より安全に効果的にマインドフルネスを取り入れられます!
【リンクのご案内】
〇カウンセラー・佐藤さんに聞く「マインドフルネス」実践と“想い”

