発達障害とマインドフルネス心理療法
2025年4月18日

発達障害とマインドフルネス心理療法
~「今ここ」に立ち返ることで見えてくる、新たな可能性~
はじめに
発達障害(自閉スペクトラム症、ADHD、学習障害など)は、生まれつきの脳の働きの特性によって、対人関係や日常生活、学業・就労の場面で困難を感じやすい状態です。近年、こうした発達障害に対する理解が進む一方で、当事者が直面する「生きづらさ」や二次的な問題(不安、抑うつ、自己否定感など)は依然として大きな課題として残っています。
そのような中で注目されているのが、「マインドフルネス心理療法」です。これは、仏教瞑想をルーツとしながらも、現代の心理療法として体系化されたもので、近年ではうつ病や不安症に限らず、発達障害の支援にも応用され始めています。
本稿では、発達障害におけるマインドフルネスの活用可能性と、その効果的な実践のヒントについてご紹介します。
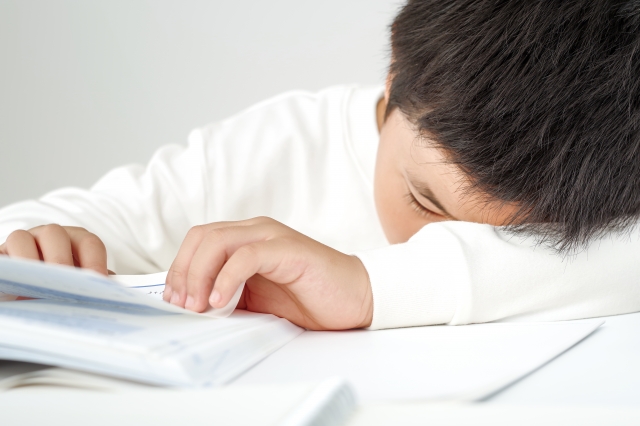
発達障害の「二次障害」とその背景
発達障害の特性そのもの(例:こだわりの強さ、注意の偏り、感覚過敏など)は、多様な個性の一部でもありますが、社会の中で「普通」とされる在り方から外れると、批判や誤解、孤立の原因にもなりやすくなります。
その結果、多くの発達障害の当事者が経験するのが、「二次障害」です。
例えば――
- 周囲に合わせられず「自分はダメだ」と思い込む自己否定感
- 同じ失敗の繰り返しによる抑うつや無気力
- 感情をうまくコントロールできないことで生じる不安やパニック
こうした心理的な苦しみは、特性の直接的な影響というよりも、「社会的なズレの中で蓄積されたストレス」によって引き起こされます。

マインドフルネスとは何か?
マインドフルネスとは、「今この瞬間」に注意を向け、評価や判断をせずに、自分の体験をあるがままに受け止める心の状態を指します。
具体的には、呼吸や身体感覚、思考、感情などの「今起きていること」に意識を向けながらも、それを良い悪いと評価せず、ただ観察する姿勢です。
マインドフルネスは、以下のような心の変化を促します:
- 刺激に対する反応を一時停止し、自分で選択できるスペースを持てる
- 思考や感情に巻き込まれず、距離をとる力(メタ認知)が高まる
- 自己批判を和らげ、自己受容が育まれる
- 衝動性や過敏さに対する気づきが深まり、感情の安定を助ける
発達障害のある方にとってのマインドフルネスの効果
マインドフルネス心理療法は、発達障害の方が抱える「内的な混乱」や「不安定な感情」「否定的な思考のループ」にアプローチする有効な手段となり得ます。
1. 感情のコントロール力を高める
発達障害の特性として、感情の起伏が激しい・衝動的になりやすいなどの傾向が見られます。マインドフルネスを通じて、「イラッとした瞬間」や「不安が高まる瞬間」に気づけるようになることで、反射的に行動するのではなく、落ち着いて選択肢を考える余地が生まれます。
2. 過剰な自己否定からの解放
「なんでこんなこともできないんだろう」と自分を責めることが習慣化している方も少なくありません。マインドフルネスでは、自分の思考や感情を評価せずに観察することを重視するため、自己否定のループから少しずつ距離をとれるようになります。
3. 社会とのズレに対する「気づき」が深まる
発達障害の方の多くは、「なぜ自分だけうまくいかないのか」と戸惑いながらも、その理由に明確な答えが持てず苦しむことがあります。マインドフルネスの実践を通じて、「自分がどのような時に混乱しやすいのか」「どんな状況が苦手か」といったパターンに気づけるようになり、それに対処する力が育ちます。

発達障害の方と接する際に気をつけること
1. 相手の特性を理解する
- 発達障害は一人ひとり異なります(自閉スペクトラム症、ADHD、学習障害など)。
- 「できない」のではなく「苦手」なことがある、という認識が大切です。
- 音や光、においなどに敏感な方もいるため、環境面にも配慮を。
2. わかりやすく、具体的に伝える
- 抽象的な表現や比喩は避け、明確で簡潔な言葉で伝えましょう。
- たとえば「ちゃんとして」よりも、「椅子にまっすぐ座ってね」の方がわかりやすいです。
3. 急な変化は避け、予告をする
- 突然の予定変更や刺激に弱い方もいます。
- スケジュールの変更があるときは、できるだけ早めに、具体的に伝えましょう。
4. 相手のペースを尊重する
- 処理速度や反応のスピードには個人差があります。
- 急かさず、待つことも大切な配慮です。
5. 否定や命令ではなく、肯定的な言葉を使う
- 「やめなさい」よりも「こうするといいよ」といった言い換えが有効です。
- 自尊心を傷つけないよう心がけましょう。
6. 安心できる関係を築く
- 「失敗しても大丈夫」「そのままでいいよ」と伝えることが、安心感につながります。
- 否定され続けてきた経験を持つ方も多いため、肯定的な関わりが何より重要です。
7. 感情のコントロールが難しいときの対応
- パニックや過敏反応が起きたときは、まず落ち着ける場所を提供しましょう。
- 叱るよりも「今はつらいね」「一緒に休もう」と寄り添う声かけを。
8. 本人の「得意」を見つける
- 苦手な部分に注目しがちですが、得意なことや興味のあることを見つけることで、自己肯定感の向上につながります。
9. 専門家と連携する
- 支援が必要な場合は、福祉サービスや心理の専門家と連携することも大切です。

発達障害には丁寧な個別対応が不可欠
なぜ発達障害には丁寧な個別対応が必要なのか?
発達障害の特性は、一人ひとり異なります。同じ診断名であっても、注意の偏りが強い人もいれば、感覚の過敏さが際立つ人、こだわりが強く行動の切り替えが難しい人もいます。つまり、「発達障害」という言葉は共通の枠組みではあるものの、実際の困りごとや得意なことは多様です。
丁寧な個別対応が必要な主な理由:
| 理由 | 説明 |
|---|---|
| 特性の現れ方が人によって異なる | 画一的な支援では合わないことが多く、逆にストレスや混乱を招くこともある |
| 小さな違和感が大きなストレスになることがある | 感覚の過敏さや、予定変更への不安など、周囲が気づきにくい困難を抱えている |
| 自己理解と安心感が土台になる | 「わかってもらえた」という実感が信頼を生み、支援への意欲や効果に直結する |
| 一般的な方法が逆効果になる場合もある | 例えば、「じっと座って話を聞く」支援が、ADHD傾向の方には負担になることも |
そのため、支援者には「相手を観察し、仮説を持ち、試行錯誤しながら関わる」という柔軟さと、本人の言葉に丁寧に耳を傾ける姿勢が求められます。
実際の支援での活用事例
当法人では、マインドフルネス心理療法を基礎とした個別支援やグループサポートを行っており、発達障害の傾向を持つ方々にも取り入れてきました。
30代男性(ADHD傾向)の例では、日々の感情の波に翻弄されていた中、マインドフルネスの実践を通じて、「今起きていることに気づき、少し待ってから行動する」習慣が身につき、家庭や職場での衝突が大きく減ったという声が寄せられました。
また、20代女性(自閉スペクトラム症傾向)では、自分の中にある「人に嫌われたくない」という強い不安に気づき、その感情を「ある」と認めることで、自分を労わる視点が持てるようになり、人間関係のストレスが軽減されました。
専門家の伴走と継続がカギ
マインドフルネスは、たしかにシンプルな実践ですが、効果を実感するまでにはある程度の継続と、的確な指導が必要です。特に発達障害の方にとっては、「感覚過敏」や「集中のしにくさ」などの特性を踏まえた工夫が重要になります。
そのため、独学での実践ではなく、発達特性に理解のある専門家のもとで、安全かつ丁寧に進めていくことが勧められます。

おわりに
発達障害という特性は、確かに社会生活において困難をもたらすことがあります。しかし、それは「欠陥」ではなく、「異なる認知のスタイル」でもあります。その人なりの強みを活かし、弱みを補う支援の一つとして、マインドフルネス心理療法は、静かに、しかし確実にその力を発揮しています。
「今、ここにいる自分を、否定せず受け入れること」
――そこから、新たな一歩が始まります。
【リンクのご案内】
〇カウンセラー・佐藤さんに聞く「マインドフルネス」実践と“想い”

