マインドフルネスとは|9つの代表的な流派・体系
2025年7月21日

マインドフルネスとは|9つの代表的な流派・体系
ここでは「マインドフルネスとは何か」という問いを踏まえながら、マインドフルネスの9つの代表的な流派・体系(例:MBSR、MBCT、ACT、CFT、Breathworks、プラムヴィレッジ、ユニファイド・マインドフルネス、マインドフルネス自己洞察法、ダルマ・マインドフルネスなど)における共通点と相違点についてわかりやすく整理してご説明します。
- マインドフルネスとは|9つの代表的な流派・体系
- マインドフルネスには多くの流派・体系がある
- 1. MBSR(マインドフルネス・ストレス低減法)
- 2. MBCT(マインドフルネス認知療法)
- 3. ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)
- 4. Breathworks(ブレスワークス)
- 5. プラムヴィレッジのマインドフルネス
- 6. Unified Mindfulness(ユニファイド・マインドフルネス)
- 7. CFT(コンパッション・フォーカスト・セラピー)
- 8. ダルマ・マインドフルネス(仏教ベースの瞑想)
- 9.マインドフルネス自己洞察法(自己洞察瞑想療法:SIMT)
- 「マインドフルネスとは何か」
- すべての流派に共通する根本的な核は、
- すべての流派で異なっていること
- ■ まとめ
- ご相談・体験セッションのご案内
マインドフルネスとは|9つの代表的な流派・体系
「今、ここ」に戻るということ ― マインドフルネスの静かな力
私たちは日々、無数の思考や感情の波の中を生きています。朝起きてから夜眠るまで、やらなければならないことに追われ、未来の不安や過去の後悔に思いを巡らせながら、気がつけば「今この瞬間」から遠く離れたところに心がさまよっている──そんな経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。
そんな私たちの心を、「今、ここ」に静かに呼び戻してくれるのが、マインドフルネスという生き方です。マインドフルネスとは、「今、この瞬間に注意を向け、評価や判断をせずに、それをあるがままに受けとめる心のあり方」と言われます。呼吸のリズム、体に生じる感覚、心に浮かぶ思いや感情。それらに気づき、それを変えようとせず、ただ見守るように注意を向けること。そんなシンプルでいて奥深い実践が、現代に生きる私たちにとって、かけがえのない支えとなりつつあります。

世界中の医療、教育、ビジネスなど様々な場面で活用される
マインドフルネスの実践は、仏教の瞑想にルーツを持ちながらも、いまや宗教的な枠組みを越えて、世界中で医療、教育、ビジネスなど様々な場面に取り入れられています。ストレス社会のうつや不安の予防、集中力の向上、睡眠の質の改善といった心身への好影響は、今や数百に及ぶ研究によって裏づけられています。
しかし、マインドフルネスが私たちにもたらす本当の変化は、単なる健康の改善だけではありません。それは、人生に対する見方そのものが変わるような、もっと根本的な気づきを含んでいます。たとえば、私たちは日常の中で、自分の感情にとらわれたり、思考の中に巻き込まれたりして、いつの間にか「自分自身」と距離が取れなくなってしまうことがあります。でも、マインドフルネスを通じて、ふと立ち止まり、「ああ、いま私はこう感じているのだな」「こんな思考が浮かんでいるんだな」と気づけたとき、私たちはその苦しみと少し距離を取ることができます。それは、自分自身に対する優しさや理解が芽生える瞬間でもあります。

例えば、痛みや不安、つらさとともに生きている人にとっては
特に、痛みや不安、つらさとともに生きている人にとって、マインドフルネスは「痛みと闘う」のではなく、「痛みとともに在る」ための大切な方法となります。ヴィディヤマラ・バーチ氏が提唱するBreathworksのプログラムは、慢性的な痛みを抱える人々にマインドフルネスを通して「生きる力」を取り戻すサポートをしています。そこでは、痛みを消すことではなく、痛みとの関係性を変えることが大切にされます。苦しみがあっても、それを柔らかく見守る心を育てていくことで、人は不思議と、より深く、穏やかに日々を生きられるようになっていくのです。
マインドフルネスの実践は、特別な場所や道具を必要としません。朝の目覚めの瞬間、コーヒーの香りを味わうひととき、通勤電車の中の揺れを感じるとき、そんな日常の中で、「今、ここにいる」ことを思い出すだけでいいのです。呼吸に意識を向けるだけでも、今この瞬間に自分を取り戻す扉がそっと開かれます。
マインドフルネスは魔法ではありません。
一度行えばすべてが変わるというものでもありません。しかし、毎日の暮らしの中で、ほんの数分でも、自分の呼吸に寄り添い、心の動きに気づき、静かに観察する時間を持つこと。それを積み重ねていくことで、私たちは少しずつ、自分自身との関係を、そして世界との関係を変えていく力を育むことができます。
「今、ここにいる」こと。それは、シンプルだけれど忘れがちな、最も大切なこと。
マインドフルネスとは、その大切さを静かに思い出させてくれる、生き方の知恵なのです。
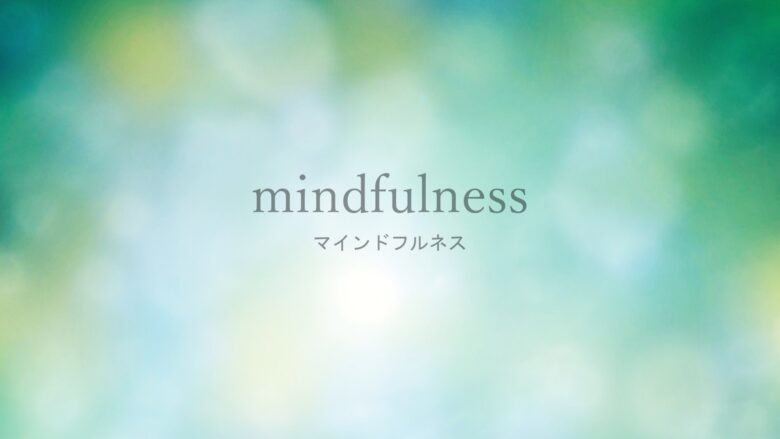
マインドフルネスには多くの流派・体系がある
起源が仏教瞑想にありながら、時代や目的に応じて変化をする
マインドフルネスのルーツは、紀元前5世紀頃に釈迦(ブッダ)によって体系化された「サティ(気づき)」にあります。しかし、その後2500年の歴史の中で、上座部仏教(ヴィパッサナー瞑想)、大乗仏教(禅など)、チベット密教など、地域ごとに異なる形で発展してきました。
それに加え、20世紀後半からは仏教の枠を超えて、心理療法や教育、ビジネス領域などへと応用されるようになり、目的や文化に合わせて多様な形に進化しました。
・具体的には以下の内容になります。
| 流派・体系名 | 主な特徴 | 主な対象 |
|---|---|---|
| MBSR | 医療的・科学的 | ストレス、慢性痛 |
| MBCT | 認知療法との統合 | うつ、不安 |
| ACT | 行動療法×受容 | 心理的柔軟性 |
| Breathworks | 痛みと共に生きる | 慢性痛、病気 |
| プラムヴィレッジ | 日常生活の気づき | 暮らし全体 |
| Unified Mindfulness | 科学的・統合的 | 理論派、瞑想指導 |
| CFT | 慈悲と回復 | 自己否定、トラウマ |
| 仏教ベース | 精神的修行 | 瞑想者、宗教心のある方 |
| 自己洞察瞑想療法(SIMT) | 医療的・科学的 | うつ、不安、ストレス |
これらは、それぞれ異なる背景や目的を持ちながら、共通して「気づき(mindfulness)」の育成を目指しています。
以下に、現代で代表的とされる主要な流派・体系をわかりやすくご紹介します。

1. MBSR(マインドフルネス・ストレス低減法)
Mindfulness-Based Stress Reduction
**MBSR(マインドフルネス・ストレス低減法)**は、1979年にアメリカ・マサチューセッツ大学医学部のジョン・カバットジン博士によって開発された、科学的かつ実践的なマインドフルネス・プログラムです。もともとは、慢性的な痛みやストレス、病気などに苦しむ人々に対して、薬や手術だけに頼らず、心の働き方を変えることで“苦しみとの関わり方”を見直す手段として考案されました。
MBSRの核となるのは、「今この瞬間に意識を向け、評価せずに観る」マインドフルネスの姿勢です。8週間のプログラムでは、ボディスキャン、坐禅、ヨーガ、歩行瞑想など、さまざまな実践を通して、日常のストレス反応に気づき、それに巻き込まれずに対処する力を育てます。自分の呼吸や身体、思考、感情に優しく注意を向けることで、反応的な習慣から距離をとり、より意図的な選択ができるようになるのです。
MBSRの特徴は、宗教色を排し、医学・心理学的な研究に基づいた実践である点です。実際に、慢性疼痛、不安、うつ、睡眠障害、がん患者の心理支援など、幅広い領域で効果が実証されており、医療機関や教育現場でも導入が進んでいます。また、MBSRはマインドフルネスの世界的広がりの原点となったプログラムでもあり、現在の多くのマインドフルネス療法(MBCT、ACTなど)の基盤にもなっています。
MBSRは、苦しみや不安を「取り除く」方法ではなく、「どう向き合い、受け入れ、共に生きるか」を学ぶ実践です。自分の内側にすでに備わっている気づきの力を目覚めさせ、穏やかで柔軟な心を育てる。それが、MBSRの本質だと言えるでしょう。
- 創始者:ジョン・カバット・ジン(Jon Kabat-Zinn)
- 特徴:医療と科学に基づいた8週間のマインドフルネス・プログラム。瞑想・ボディスキャン・ヨガなどを通じて、ストレス、慢性痛、心身の不調と向き合う。
- 対象:医療患者(がん、不眠、痛みなど)から一般の人まで幅広く応用。
📌現代マインドフルネスの基礎を築いた最も有名な体系。

2. MBCT(マインドフルネス認知療法)
Mindfulness-Based Cognitive Therapy
**MBCT(マインドフルネス認知療法)**は、うつ病の再発を防ぐために開発された心理療法で、マインドフルネスの実践と認知行動療法の要素を組み合わせたアプローチです。1990年代後半に、イギリスの心理学者ジョン・ティーズデール、マーク・ウィリアムズ、ジンダ・シーガルらによって開発されました。特に、うつ病から回復した人が再び落ち込む「再発のサイクル」を断ち切るために、有効な方法として世界中で注目を集めています。
MBCTの基本的な考え方は、「ネガティブな思考が浮かぶこと自体を止めようとするのではなく、その思考に気づき、巻き込まれずに距離をとる力を育てる」というものです。人は、気分が落ち込んでいるとき、「またダメだ」「どうせうまくいかない」といった自動的な思考にとらわれがちです。MBCTでは、こうした思考を“問題として解決すべきもの”ではなく、“ただの心の動き”として観察し、それにとらわれない新しい関わり方を身につけます。
具体的には、8週間のプログラムを通じて、ボディスキャンや呼吸瞑想、日常の中の気づきの練習などが行われます。また、従来の認知療法の技法も取り入れながら、気分や思考のパターンに気づくワークも組み込まれています。その結果、気分が下がったときに“自動操縦”でネガティブな思考に流されるのではなく、「今ここに戻る力」が養われます。
科学的研究でも、MBCTはうつ病の再発予防に高い効果を示しており、特に過去に3回以上うつ病を経験した人に対しては、薬物療法と同程度の効果があると報告されています。また、不安障害やストレス、慢性痛などへの応用も進められており、心の回復力(レジリエンス)を高める実践として評価されています。
MBCTは、「苦しみを完全に無くす」のではなく、「苦しみに対して新しい視点と態度を育てる」療法です。思考や感情に巻き込まれず、あるがままに気づく力。それこそが、再び心の嵐に巻き込まれないための土台となるのです。
- 創始者:ジンドル・シーゲル、マーク・ウィリアムズら(認知行動療法の研究者)
- 特徴:MBSRを土台に、うつ病の再発予防を目的として認知行動療法(CBT)を組み合わせた8週間プログラム。
- 対象:再発性うつ病、不安症、ネガティブな思考パターンを持つ人。
📌心理療法にマインドフルネスを統合した代表的アプローチ。

3. ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)
Acceptance and Commitment Therapy
**ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)**は、1990年代にアメリカの心理学者スティーブン・C・ヘイズらによって開発された、新しいタイプの認知行動療法です。ACTは「アクセプタンス(受け入れ)」と「コミットメント(価値に基づいた行動)」という2つの柱を中心に、人生の困難や内的な痛みに柔軟に向き合いながら、自分が本当に望む生き方を実現していく心理的アプローチです。
従来の認知行動療法では、不安やうつ、ネガティブな思考を「変える」「正す」ことが目標とされてきましたが、ACTではそれらを“無理に変えようとしない”という独自の立場をとります。むしろ、苦しみや不快な感情は人間として自然なものであり、それを避けようとするほど苦しみが深まると考えます。そこでACTは、「感情や思考を受け入れながらも、自分の価値に沿った行動をとる」という柔軟な生き方を提案します。
ACTの実践では、6つの心理的スキルが重視されます。たとえば、「今この瞬間に意識を向けるマインドフルネスの力」、「思考と距離をとる脱フュージョン」、「自分の感情や痛みを受け入れる姿勢」、「自分にとって本当に大切な価値を明確にすること」、そして「その価値に基づいて行動を選ぶ力」などです。これらのスキルを通じて、人はより柔軟に、困難を抱えながらでも豊かな人生を歩むことができるようになります。
ACTは、うつ病や不安障害、PTSD、慢性痛、依存症、職場のストレスなど、さまざまな領域で効果が確認されており、教育、スポーツ、ビジネスの分野でも活用が広がっています。特に「コントロールではなく関係性を変える」という視点が、多くの人にとって解放感をもたらし、持続可能な変化を促す点で注目されています。
ACTは、苦しみを取り除くことよりも、「苦しみを抱えながらも、自分らしく生きる力」を育てる心理療法です。不安や悲しみがあっても、その奥にある“生きたい方向”に向かって、意図的に一歩を踏み出す。そんな生き方を支えてくれるのが、ACTの魅力だと言えるでしょう。
- 創始者:スティーブン・C・ヘイズ(認知行動療法第3世代)
- 特徴:マインドフルネスを「今この瞬間の経験への受容」として扱い、価値に基づく行動変容を促す。
- 対象:うつ、不安、トラウマ、依存症など多様な心理的課題。
📌「痛みはあっても苦しみを減らす」ことに焦点をあてる。

4. Breathworks(ブレスワークス)
**Breathworks(ブレスワークス)**は、慢性の痛みやストレス、心の苦しみを抱える人々のために開発された、実践的なマインドフルネス・プログラムです。その創始者であるヴィディヤマラ・バーチ氏は、10代のときに脊髄損傷を負い、以後も長年にわたって重度の慢性疼痛と共に生きてきました。彼女自身の苦しみの経験と、それを和らげるために出会ったマインドフルネスと慈悲の瞑想が、Breathworksの源となっています。
Breathworksは、仏教の瞑想法を背景に持ちつつも、誰でも取り組める形に洗練されており、医療・福祉・教育現場でも広く活用されています。特に慢性疼痛や身体疾患による不快感、またストレスや不安などの心身の負担を抱える人たちに対して、苦しみを“無くす”のではなく、“新しい関係性を築く”ことを目指しています。
プログラムの中心は、マインドフルネスとセルフ・コンパッション(自分への思いやり)を育てる実践です。呼吸への意識を通じて「今この瞬間」に戻り、身体感覚、感情、思考をやさしく見守る力を養います。特に特徴的なのが、「呼吸と共にある慈悲の瞑想」で、これは痛みや苦しみに直面しながらも、自己への慈しみと落ち着きを育てる効果があるとされています。
Breathworksでは、苦しみの構造を「一次の痛み」と「二次の痛み」に分けて捉えます。一次の痛みは身体的・現実的なものですが、そこに「こんなはずじゃない」「なぜ自分だけが」といった思考や感情が重なることで、苦しみが拡大していきます。Breathworksは、この“二次的な苦しみ”への気づきを促し、より柔らかく、優しい意識で接する在り方を育てます。
科学的な研究においても、Breathworksプログラムは慢性疼痛の緩和、不安や抑うつの軽減、生活の質の向上に効果があることが示されており、特に欧州を中心に多くの医療・福祉従事者に支持されています。
Breathworksは単なるテクニックではなく、「どんな状況でも、自分を慈しみ、今を生きる力を取り戻す」ための、生き方の実践です。痛みと共に歩む人々にとって、深い癒しと勇気をもたらす道となるでしょう。
- 創始者:ヴィディヤマラ・バーチ(Vidymala Burch)
- 特徴:自身の慢性痛の経験から開発された、痛みやストレスへの慈悲と気づきを育てるプログラム。MBSRに慈悲の実践(コンパッション)を組み合わせている。
- 対象:慢性疼痛、障害、ストレス、病気とともに生きる人々。
📌「痛みとともに生きる」ためのマインドフルネスの実践。

5. プラムヴィレッジのマインドフルネス
Thích Nhất Hạnh(ティク・ナット・ハン)師による伝統的実践
プラムヴィレッジのマインドフルネス実践は、ベトナム出身の禅僧・詩人・平和活動家である**ティク・ナット・ハン(Thich Nhat Hanh)**師によって創始された、日常生活と深く結びついたマインドフルネスの在り方です。1982年に南フランスの田園地帯に設立された仏教共同体「プラムヴィレッジ」は、単なる瞑想センターではなく、マインドフルに「今ここ」を生きることを学ぶ修道院・学び舎であり、現在では世界中の人々が訪れる精神的拠点となっています。
プラムヴィレッジの実践の特徴は、「マインドフルネスを特別な時間に限らず、食事、歩行、掃除、会話など、すべての日常の行為の中で育てていく」点にあります。つまり、瞑想とは座って目を閉じるだけのものではなく、一呼吸ごとに意識を今この瞬間に戻し、人生そのものを丁寧に味わうことなのです。
特に大切にされている実践には、「歩く瞑想」「食べる瞑想」「微笑みの呼吸」などがあり、どれもシンプルながら深い癒しと気づきをもたらします。たとえば、歩く瞑想では「一歩ごとに平和を感じ、一歩ごとに大地とつながる」ことを意識します。呼吸と歩みを調和させながら、自分の存在が自然と一体であることを感じていきます。
ティク・ナット・ハン師の教えは、非暴力、共感、深い聞き方(ディープ・リスニング)などを重視し、個人の癒しだけでなく、家族や社会、地球環境に対する責任をも含んでいます。彼は「マインドフルネスは、私たちが世界の苦しみに目を背けずにいながら、それに飲み込まれないための力」であると語り、社会変革とスピリチュアルな実践を統合する稀有な教えを伝えてきました。
プラムヴィレッジのマインドフルネスは、宗教や信仰の枠を超えて、多くの人々に静かな感動と深い気づきをもたらしています。穏やかな呼吸と共に「今ここに在る」ことを学ぶこの実践は、現代の忙しさや不安に満ちた世界の中で、心の拠りどころとなる大きな力を秘めています。
- 創始者:ティク・ナット・ハン(ベトナムの禅僧、詩人、平和活動家)
- 特徴:日常生活すべてが瞑想であるとする「生きるマインドフルネス」。歩く、食べる、話すなど、すべての行為に気づきと慈悲を向ける。
- 対象:宗教を問わず日常に実践を取り入れたい人。
📌「微笑みの瞑想」「歩行瞑想」など、温かく平和的なスタイルで人気。

6. Unified Mindfulness(ユニファイド・マインドフルネス)
**Unified Mindfulness(ユニファイド・マインドフルネス)は、アメリカの瞑想指導者であり研究者でもあるシン・ゼン・ヤン(Shinzen Young)**によって体系化された、非常に明確で実践的なマインドフルネスのトレーニング法です。これは仏教の伝統的な瞑想法を土台にしながらも、現代の心理学や神経科学、教育など多様な分野に応用できるように、洗練された「技術としてのマインドフルネス」を目指しています。
ユニファイド・マインドフルネスの特徴は、その明確さと構造性にあります。マインドフルネスの実践を「集中力(Concentration)」「感覚の明晰さ(Sensory Clarity)」「平静さ(Equanimity)」という3つのスキルに分け、それらを高めるための具体的な瞑想法が丁寧に設計されています。これは、初心者にも熟練者にも有益で、個々の目的や状況に応じて柔軟に実践を組み立てることができます。
実践方法は、「See(見る)」「Hear(聞く)」「Feel(感じる)」という3つの感覚チャンネルに基づいた瞑想が中心です。たとえば、目を閉じて心の中に現れるイメージや思考を「See In(内側の視覚)」として観察したり、外界の音を「Hear Out(外の聴覚)」として意識的に聞く、というように、自分の体験を明確に分類しながら意識を向けていきます。このプロセスを通じて、心の動きに自覚的になり、巻き込まれずに観察する力が育まれます。
また、ユニファイド・マインドフルネスはその名のとおり、「統一された」実践体系であり、宗教色を排しながらも、仏教的な知恵を現代的に翻訳したものです。そのため、ビジネスパーソン、医療者、教育者、スポーツ選手など、宗教にとらわれずに実用的なマインドフルネスを学びたい人々から高く支持されています。
さらに、科学的研究との親和性も高く、脳神経科学や臨床心理学の分野でその効果が検証されています。実際に、うつ、不安、慢性痛、ADHD、ストレス管理などへの応用も進められており、現代社会のニーズに即したマインドフルネス実践として注目されています。
ユニファイド・マインドフルネスは、「今ここ」の体験に深く入り込み、人生のあらゆる瞬間を学びと成長の機会として開いていくための実践的な道です。瞑想という内面の技術を、誰にとっても扱いやすい形で届ける――その哲学と構造の明快さは、まさに現代マインドフルネスの最前線と言えるでしょう。
- 創始者:シン・ゼン・ヤン(Shinzen Young)
- 特徴:瞑想体験を明確に言語化し、科学的アプローチと統一的なフレームワークで整理した実践法。集中力、感覚、慈悲などを明確に分類。
- 対象:科学的、理論的に学びたい人/瞑想指導者の訓練にも。
📌シリコンバレーやIT業界などでの導入が進む。
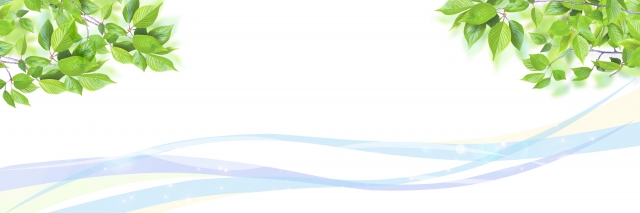
7. CFT(コンパッション・フォーカスト・セラピー)
Compassion-Focused Therapy
**コンパッション・フォーカスト・セラピー(CFT)**は、イギリスの臨床心理学者ポール・ギルバート(Paul Gilbert)によって開発された心理療法で、自己批判や恥、自己否定の感情に苦しむ人々を対象に、**思いやり(コンパッション)**の心を育てていくことを中心に据えています。CFTは、うつ、不安、トラウマ、摂食障害などの背景にある「自分への厳しさ」に着目し、心の痛みに寄り添いながら回復を促すアプローチとして注目されています。
CFTの基本的な考え方は、人の心には3つの感情システム(脅威システム、動機づけ・達成システム、安心・癒しシステム)があり、そのバランスの崩れが心理的苦痛を引き起こすというものです。たとえば、脅威システムが過剰に活性化していると、不安や自己批判が強まり、苦しみが慢性化します。CFTでは、**安心・癒しのシステム(=コンパッション)**を活性化させることで、心の安定と自己への優しさを取り戻していきます。
このセラピーでは、マインドフルネスやイメージトレーニング、身体感覚への気づきなどの技法を用いながら、自己への思いやりを育てる実践を重ねていきます。たとえば、「コンパッションのある自己」をイメージし、その存在からの言葉や態度を心に描くことで、自分の中に安全で温かい関係性を築いていくことを目指します。また、過去の恥やトラウマに対しても、否定せず、優しさを持って向き合う姿勢が奨励されます。
CFTの大きな特徴は、「コンパッションは甘やかしではない」という立場をとっていることです。むしろ、困難と向き合い、勇気を持って行動するための内的な強さとしてのコンパッションを強調します。つまり、CFTが育てようとするのは「弱さに逃げる優しさ」ではなく、「痛みに直面しつつ、それを理解し、支えようとする力強い優しさ」なのです。
CFTは、マインドフルネスやACT、DBTなどとも共通点を持ちながら、特に「自分を責める声」との関係性に重点を置いたアプローチです。自己批判が強い人、自分に価値を感じにくい人にとって、このセラピーは新しい視点と温かい癒しをもたらしてくれるでしょう。現在では、臨床だけでなく教育、福祉、職場などでも応用が進められており、「思いやりは人を変える力がある」というCFTの理念が広がりつつあります。
- 創始者:ポール・ギルバート
- 特徴:自己批判や恥に苦しむ人々のために、慈悲(コンパッション)を軸としたマインドフルネスと心理療法を組み合わせたアプローチ。
- 対象:強い自己否定感をもつ人、トラウマからの回復。

8. ダルマ・マインドフルネス(仏教ベースの瞑想)
ダルマ・マインドフルネスとは、仏教の伝統的な教えと実践に根ざしたマインドフルネスのアプローチを指します。「ダルマ(Dharma)」とは、仏教における真理や教え、法を意味する言葉であり、ダルマ・マインドフルネスは、単なるストレス軽減や集中力向上の手段ではなく、心の深い自由と目覚めを目指す道として位置づけられています。
仏教におけるマインドフルネス(サティ)は、「四念処(しねんじょ)」と呼ばれる基本的な実践に支えられています。これは、①身体(カヤ)②感受(ヴェーダナー)③心(チッタ)④法(ダンマ)という四つの対象に気づきを向ける方法で、それぞれの領域を観察することで、無常・苦・無我という三法印への理解が深まり、煩悩からの解放へとつながります。
ダルマ・マインドフルネスの実践では、呼吸や身体感覚を入り口に、「今ここにある体験」に意識をとどめることから始めますが、その目的は単なるリラックスではなく、煩悩に気づき、智慧と慈悲を育むことです。思考や感情、欲望や怒り、恐れなどの内的現象に対して、判断せず、執着せず、あるがままに観察することで、それらが自分の本質ではなく、ただの一時的な現象であることが明らかになっていきます。
多くの現代的マインドフルネス・プログラムは、この仏教的なマインドフルネスから影響を受けていますが、ダルマ・マインドフルネスは、特にその**倫理性(シーラ)と智慧(パニャー)**の育成を重視します。つまり、「自他に対して harm(害)を与えない生き方」を土台としながら、物事の本質を見抜く洞察力を養うことが実践の中心にあります。
このような実践は、ヴィパッサナー瞑想(洞察瞑想)や、ティク・ナット・ハン師のプラムヴィレッジ、または上座仏教や禅など、さまざまな仏教の流派で長い年月をかけて培われてきました。いずれも共通して、「自分自身の苦しみと向き合い、それを理解し、手放す力を育む」という点において、深い癒しと変容を促します。
ダルマ・マインドフルネスは、単なる自己改善のツールではなく、「いかに生きるか」という根源的な問いに向き合う道です。忙しく複雑な現代社会の中で、静かな気づきと内なる平和を育てたいと願う人々にとって、その教えと実践は、変わらぬ光を放ち続けています。
- 代表:サティパッターナ瞑想(気づきの基礎)、ヴィパッサナー瞑想など
- 特徴:ブッダの教えに基づいた瞑想実践。仏教修行と現代心理学の融合に興味がある人に向いている。
- 対象:より伝統的な瞑想や精神性に触れたい人。
📌宗教的な背景を大切にした深い内省的実践。

9.マインドフルネス自己洞察法(自己洞察瞑想療法:SIMT)
- 正式名称:Self-Inquiry based Mindfulness Therapy(SIMT)
- 開発者:太田健次郎
- 哲学的背景:西田幾多郎の「純粋経験」を基盤に、「自己とは何か」を深く掘り下げる内面的な洞察を重視
- 出版元:佼成出版社より実践書・解説書が刊行
特徴
- 仏教的瞑想や西田哲学を背景に、「今、ここ」に生起する思考・感情・身体感覚に明晰に気づき、その背後にある**自動的認知(自動思考)**を洞察する。
- 行動療法や認知療法の枠組みとは異なり、「自己の本質に気づく」ことを最終的な目的とする。
- 実践には「気づきの記録」などの内省ワークも含まれる。
他の流派との違い
SIMTは、欧米のMBSRやMBCTが扱う「苦痛の軽減」や「ストレス緩和」にとどまらず、存在論的自己理解にまで踏み込む点が特長です。
これは、単なる「症状改善」ではなく、自己の在り方そのものへの深い気づきと変容を目指しているという点で、哲学的にも実践的にもユニークです。
「マインドフルネスとは何か」
ここからは「マインドフルネスとは何か」という問いを踏まえながら、9つの代表的な流派・体系(例:MBSR、MBCT、ACT、CFT、Breathworks、プラムヴィレッジ、ユニファイド・マインドフルネス、マインドフルネス自己洞察法、ダルマ・マインドフルネスなど)における共通点と相違点についてわかりやすく整理してご説明します。
すべての流派に共通する根本的な核は、
1. 「今この瞬間」に気づきを向ける
すべての流派に共通する根本的な核は、現在の体験(感覚・思考・感情など)に対して、評価や判断を加えずに気づきを向けることです。これはどの流派でも変わりません。
2. 苦しみに向き合う姿勢
マインドフルネスの実践は、ストレス、痛み、自己批判、不安、うつなどの苦しみに巻き込まれず、観察し、受け容れる力を育てることを目指します。これは宗教的でも、医療的でも同様に見られます。
3. 自己理解と変容の可能性
意識的に「気づく」力が養われることで、反応的だった心のパターンに変化が起き、自己理解が深まり、柔軟な選択が可能になるという点も共通しています。
4. 実践に基づく体験の重視
いずれの流派も、「読むこと・知ること」だけでなく、「実践すること(座る・呼吸する・観察する・感じる)」を重視します。体験の中から気づきを得ることが大切だとされています。
すべての流派で異なっていること
1. 目的・文脈
- MBSR・MBCT:医療や心理療法の中でストレス・うつへの対応を目的とする。
- ACT・CFT:心理療法としての応用に特化。特に価値観や思いやりの強化を重視。
- Breathworks:慢性痛や身体疾患のある人へのケアに焦点をあてた実践。
- プラムヴィレッジ・ダルマ系:仏教の哲学と倫理に根ざし、解脱や慈悲の育成を重視。
- ユニファイド・マインドフルネス:科学的で構造化されており、一般向け・技術志向。
- マインドフルネス自己洞察法:西田哲学に基づく、自己を深く内省する日本発の方法論。
2. 方法・技術
- ACTやCFTは認知行動療法やイメージワークと結びついた独自の技法が含まれています。
- ユニファイド・マインドフルネスは感覚チャンネルごとの意識化など、極めて精密な技術体系を持ちます。
- **仏教系(ダルマ、プラムヴィレッジなど)**は慈悲の瞑想や歩く瞑想などが重視されます。
3. スピリチュアル性の強さ
- MBSRやMBCT、ACTなどは非宗教的で、中立性を保った設計。
- プラムヴィレッジ、ダルマ、などは、宗教的・哲学的背景が色濃く反映されています。
■ まとめ
マインドフルネスの体系は、背景や技法、目的こそ異なりますが、根底には共通した「今に気づくことを通じて苦しみから自由になる」という意図があります。
違いは、「その自由をどう定義するか」、「どの方法でそれを育むか」にあります。宗教的な伝統に則って行う人もいれば、心理療法や日常生活のストレス対処法として行う人もいます。
それぞれの流派や体系は、その人の関心・人生の課題・文化的背景に応じて選ばれるべきものです。そして、どの道も最終的には、「慈しみと気づきを持って、自分と他者を大切に生きること」へと向かっています。
ご相談・体験セッションのご案内
もし今、ストレスやうつ病・不安症等の精神疾患痛でお悩みの方、ご家族の方で「このままでいいのか…」「少しでも楽になりたい」と思われているなら、ぜひお気軽にご相談ください。
オンライン無料相談・体験セッションも随時受付中です。

【リンクのご案内】
〇カウンセラー・佐藤さんに聞く「マインドフルネス」実践と“想い”

