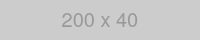抗不安薬や抗うつ薬の副作用に付いて
2025年4月21日

うつ病や不安症(不安障害・パニック障害)などの精神疾患になってしまうと、医師の診断を受けることが大切になります。すると、その方の症状に応じて投薬治療などの処方になります。
そこで処方される抗不安薬や抗うつ薬には、精神的な症状の緩和には一定の効果がありますが、同時に副作用も存在します。その為に処方薬の効果と副作用の説明をきちんと伺った上での服用が大切になります。
しかし、効果の説明はされるのですが副作用についてはあまりされていないように思いますので、以下に、主な副作用とその特徴をわかりやすく説明しますので、参考にしてください。
【抗不安薬の副作用】
抗不安薬には、主にベンゾジアゼピン系が使われています。これは即効性があり、不安や緊張を和らげる作用があります。
主な副作用:
- 眠気・注意力の低下
日中でも強い眠気が出ることがあります。運転や機械操作には注意が必要です。 - ふらつき・転倒リスク
高齢者では特に注意が必要で、筋力やバランス感覚が一時的に低下することがあります。 - 依存性
長期間使用すると、薬に対する「身体的・心理的依存」が生じることがあります。急にやめると**離脱症状(不安、イライラ、けいれんなど)**が出ることもあります。 - 記憶力や判断力の低下
長期使用により、物忘れが増えたり、判断力が鈍ることがあります。
【抗うつ薬の副作用】
抗うつ薬にはいくつかの種類がありますが、最近よく使われるのは**SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)やSNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)**です。
SSRI・SNRIの副作用:
- 吐き気・胃の不快感
服用初期に多く見られ、数日~1週間程度で落ち着くことが多いです。 - 不眠・焦燥感
一時的に眠りにくくなったり、逆に不安感が強まることがあります。 - 性機能の低下
性欲減退、勃起障害、オーガズム障害などが見られることがあります。 - 体重増加・減少
薬によって異なりますが、代謝や食欲に影響を与えることがあります。 - 感情の平坦化
喜びや悲しみの感情が鈍くなり、感情表現が乏しくなることがあります。
【その他の注意点】
- 開始時や増量時に副作用が出やすいため、少量から始めて徐々に増やすのが一般的です。
- 自分の判断で急にやめるのは危険で、必ず医師の指示を仰ぐことが大切です。
- 副作用は個人差が大きいため、「合う薬」を見つけるまでに時間がかかることもあります。
補足:副作用が不安な方へ
マインドフルネスや心理療法と併用することで、薬の量を抑えたり、依存のリスクを減らすことも可能です。精神的なケアをトータルで考えることが大切です。

【副作用との上手な付き合い方】
1. 副作用を記録する
副作用がいつ、どんな場面で出たかをメモしておくと、医師に伝えやすくなり、薬の調整や変更の参考になります。
たとえば:
- 「朝飲むと昼に強い眠気が出る」
- 「性欲が落ちたのは薬を変えたタイミングと一致する」
2. 薬の服用時間を調整する
眠気や胃の不快感が出る場合は、医師の指示をもとに服用時間を夜にずらすなどの調整が可能なこともあります。
3. 医師に相談して少量から試す
副作用を減らすために、「最小有効量」で始める方法もあります。急な増量は避けることで、体が慣れる時間を確保できます。
4. 生活習慣を整える
薬だけに頼らず、睡眠・食事・運動を意識することで、体調全体を安定させやすくなります。副作用の感じ方も変わることがあります。

【薬を使わない/減らす選択肢】
薬を完全にやめることが適しているかどうかは個人によりますが、「他の方法と併用して、薬を減らしていく」「再発予防に薬以外を使う」などの選択もあります。
1. マインドフルネス(瞑想)
不安や抑うつの根本的な部分(自動思考・反応パターン)に働きかけることができ、薬とは違ったアプローチで精神を落ち着ける方法です。
継続することで、再発率を下げるという研究結果もあります。
2. 認知行動療法(CBT)
思考パターンや行動のクセを見直す療法で、うつ病・不安障害ともに高い効果があります。薬の代わりに第一選択とされることもあります。
3. サポートグループやピアサポート
同じような経験を持つ人と話すことで、「自分だけではない」と安心感が得られ、ストレス軽減にもつながります。
4. 運動療法(特に有酸素運動)
ウォーキングや軽いジョギングなどが、セロトニンやドーパミンの自然な分泌を促すことが分かっています。薬と同程度の効果があるという報告も。
5. 自然療法・栄養療法
栄養不足が精神状態に影響している場合、ビタミンB群、マグネシウム、オメガ3脂肪酸などの補給で改善する例もあります。

【薬をやめるときの注意点】
- 自分の判断で急に中止しないこと
離脱症状が出る場合がありますので、医師と相談しながら少しずつ減らしていく必要があります。 - 精神的なサポートを併用する
薬を減らすと、不安や抑うつがぶり返す可能性があります。マインドフルネスやカウンセリングなどを同時に行うと安定しやすくなります。
補足:安心して相談できる場所が大切
もし、病院で「薬をやめたい」と言いにくかったり、不安があれば、私たちのような第三者の心理支援サービスを活用して、一緒に方向を探っていくこともできます。
【副作用との上手な付き合い方】
1. 副作用を記録する
副作用がいつ、どんな場面で出たかをメモしておくと、医師に伝えやすくなり、薬の調整や変更の参考になります。
たとえば:
- 「朝飲むと昼に強い眠気が出る」
- 「性欲が落ちたのは薬を変えたタイミングと一致する」
2. 薬の服用時間を調整する
眠気や胃の不快感が出る場合は、医師の指示をもとに服用時間を夜にずらすなどの調整が可能なこともあります。
3. 医師に相談して少量から試す
副作用を減らすために、「最小有効量」で始める方法もあります。急な増量は避けることで、体が慣れる時間を確保できます。
4. 生活習慣を整える
薬だけに頼らず、睡眠・食事・運動を意識することで、体調全体を安定させやすくなります。副作用の感じ方も変わることがあります。

【薬をやめるときの注意点】
- 自分の判断で急に中止しないこと
離脱症状が出る場合がありますので、医師と相談しながら少しずつ減らしていく必要があります。 - 精神的なサポートを併用する
薬を減らすと、不安や抑うつがぶり返す可能性があります。マインドフルネスやカウンセリングなどを同時に行うと安定しやすくなります。
補足:安心して相談できる場所が大切
もし、病院で「薬をやめたい」と言いにくかったり、不安があれば、私たちのような第三者の心理支援サービスを活用して、一緒に方向を探っていくこともできます。

【マインドフルネスを用いた減薬サポートの全体像】
目的:
- 薬に頼りすぎずに自分自身の内面の回復力を育てる
- 副作用の影響を受けにくくする
- 減薬・断薬の際に起こる心身の反応をやさしく観察しながら整える
【具体的ステップと内容】
🔹ステップ1:心身の観察習慣をつける(最初の2週間)
目的:今の状態(不安・眠気・胃の調子など)に「気づく」ことから始める
方法:
- 1日5〜10分の「呼吸瞑想」または「ボディスキャン」
- 気づいたことを「記録(ジャーナル)」する(例:朝、頭が重い・不安が強い)
- 服薬後の体調も記録
→ 副作用の現れ方や、時間帯ごとの気分の波が見えてきます。
🔹ステップ2:感情や思考への「巻き込まれ」を減らす(3〜6週間目)
目的:離脱症状や副作用に対する「過剰な不安」をやわらげる
方法:
- 「気づきの瞑想」:浮かんでくる思考や感情をただ観察する練習(判断せずに)
- 「ラベリング」:思考が浮かんだら、「これは思考」「これは不安」と名前をつけて距離を取る
→ 体や心の変化に過剰反応せず、落ち着いて対応できるようになります。
🔹ステップ3:日常生活にマインドフルネスを取り入れる(7〜12週間目)
目的:安定した心の土台を日常の中でも築く
方法:
- 「食べる瞑想」や「歩く瞑想」など、生活の一部を丁寧に味わう
- スマホや刺激から少し距離を置き、五感の感覚に意識を向ける習慣を作る
→ 薬が減ったときにも、環境や自分を整えるスキルが身につきます。
🔹ステップ4:医師との連携と減薬の計画(並行して進める)
目的:安全な形で薬を減らす
方法:
- 主治医にマインドフルネスを実践していることを伝え、ゆっくりと段階的な減薬を相談
- 減薬期間中も、マインドフルネスを続けて心の安定を維持
→ 減薬による離脱症状が軽減される可能性があります。
【副作用への対処に使えるマインドフルネス技法】
| 副作用の種類 | 有効なマインドフルネス練習 | 備考 |
|---|---|---|
| 眠気、集中力低下 | 呼吸瞑想、歩く瞑想 | 頭をスッキリさせるリズムを作る |
| 不安感の増加 | 気づきの瞑想、ラベリング | 不安に巻き込まれにくくなる |
| 感情の鈍麻 | 五感に集中する瞑想 | 音、香り、手触りなどの感覚を研ぎ澄ます |
| 胃の不快感 | ボディスキャン | 身体の声に気づき、緩和されることがある |
補足:個別サポートを希望される方へ
私たちが提供しているような、**マンツーマン形式の「マインドフルネス心理サポート」**では、
- 減薬中の不安な時期に一緒にマインドフルネスを行い、
- 状況に合わせて瞑想やセルフケアをカスタマイズするサポート
なども行っています。
マインドフルメイトの相談会
マインドフルメイトでは、マインドフルネス心理療法を用いて、精神疾患の治療及び予防を行っています。その対策や予防が出来ずに過ごしてしまうと症状が長引くと仕事ができない、思うことができないと苦悩したり、悪化すると自殺したい、消えたいなどの気持ちが出てくる人がいます。マインドフルネス心理療法は、アメリカの臨床実験により、うつ病や不安障害やパニック障害やPTSD、摂食障害(拒食・過食)、依存症、家族の不和などに効果があることが確認されています。
以下をご覧ください。(クリック)↓ https://mindfulmate.jp/conference/
マインドフルネスのエビデンス(効果の検証)
マインドフルメイトでは、過去10年以上の活動データを基にエビデンスを制作しています。その方たちは、うつ病や不安障害・パニック障害等の症状で悩む方々になります。私たちは、それらの方々の苦しみの声に真摯に耳を傾け、その人・その人に相応しいマインドフルネスを提供してきました。
その結果が、10年間で600名以上になっていますのでその集約をマインドフルネスのエビデンスとしています。
以下をご覧ください。(クリック)↓ https://mindfulmate.jp/evidence/
この記事は以下の方が執筆しています。
 佐藤福男
佐藤福男
〇資 格 : マインドフルネス瞑想療法士(マインドフルネス総合研究所) マタニティー / 0才児 指導者資格(幼児開発協会) 一般旅行業取扱主任者(国家資格) 〇役 職: 非営利型一般社団法人マインドフルメイト代表理事・ マインドフルネス学校 学校長
【リンクのご案内】
〇カウンセラー・佐藤さんに聞く「マインドフルネス」実践と“想い”
![]() https://mindfulmate.jp/practice-of-mindfulness-and-feelings/
https://mindfulmate.jp/practice-of-mindfulness-and-feelings/
〇うつ病や不安障害を乗り越えた体験談
![]() https://mindfulmate.jp/impressions-after-the-mindfulness-session/
https://mindfulmate.jp/impressions-after-the-mindfulness-session/
〇マインドフルネス相談会のご案内 IN東京都・愛知県・山梨県
![]() https://mindfulmate.jp/conference/
https://mindfulmate.jp/conference/
〇マインドフルネスのエビデンス / 調査・研究・活動の報告
![]() https://mindfulmate.jp/evidence/
https://mindfulmate.jp/evidence/
〇マインドフルメイトのサイトマップ